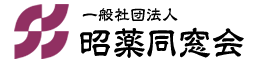代表理事挨拶

同窓会会員の皆様におかれましては益々ご健勝で、ご活躍のこととお喜び申し上げます。 また、平素より同窓会活動に格別のご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
令和5年6 月の臨時理事会の推薦で選任され、ご承認をいただき、逸見仁道前会長の後を受けて代表理事を務めさせて頂くこととなりました、昭和49年卒の田口恭治と申します。私は昭和薬科大学4年間、大学院修士課程2年間の修了後に薬理学研究室の助手として採用され、薬理学を学びました。平成9年から薬学教育の6年制の移行に伴い新たに新設された薬物治療学研究室、その後、薬品作用学教育研究室と38年間お世話になりました。この間、野球部・バスケット部の顧問としても多くの学生と一緒に活動させて頂きました。私自身この昭和薬科大学で繋いだ縁を大切にしております。同窓生の皆様にも、昭和薬科大学で出会った同級生、後輩、先輩や先生方のことを思い出し、その縁を次の世代にも繋いでほしいと思っています。 同窓会はクラス会や全国の支部会の活動や開催を支援し、そして同窓生の縁を先輩−同級生−後輩の縦−横に強く結べたらと考えています。
昭薬同窓会の定款の第2条には「会員相互の親睦と研修を図り、昭和薬科大学の発展に寄与貢献することを目的とする」とあります。昭薬同窓会の平成塾は生涯研修認定制度の研修機関(プロバイダー)として、公益社団法人薬剤師認定制度認証機構(Council on Pharmacists Credentials: CPC)より認証され認定薬剤師の取得も可能です。研修単位は他の研修機関と互換性があり多くの同窓生が取得しています。さらに、薬剤師業務支援講座を年4回WEBで開催し、病院・薬局で勤務する同窓生を講師として招き、生涯学修の場としても活動を続けてまいります。さらに、経済的に困窮する学生を支援すべく、給付型の昭薬同窓会奨学金を立ち上げる予定です。
近年、残念ですが同窓会員数が減少傾向にあります。こういう時にこそ、老壮青のバランスが必要であると考えております。今後は、6年制の同窓会員の方々にどのような形で参画をして頂くかを含め、同窓会の改革を目指して頑張っていきます。同窓会の運営は同窓生のご協力なくしては運営できません。同窓会会員皆様のあたたかいご支援ご協力を頂きながら、創立 100周年を迎えた母校と同窓会の更なる発展に尽力していきたいと考えています。
【略歴】
昭和薬科大学生物薬学科卒業、同大学院薬学研究課修士課程修了
同薬理学研究室 助手、講師、准教授
同薬物治療学研究室 准教授
同医療薬学教育センター医療薬学部門・薬品作用教育研究室 教授
学校法人昭和薬科大学評議員、昭和薬科大学名誉教授
米国イリノイ州立大学医学部留学 Rockford 校
薬学博士(大阪大学)